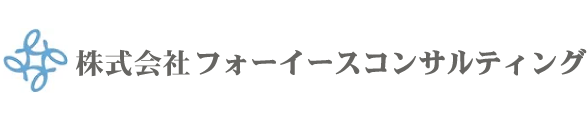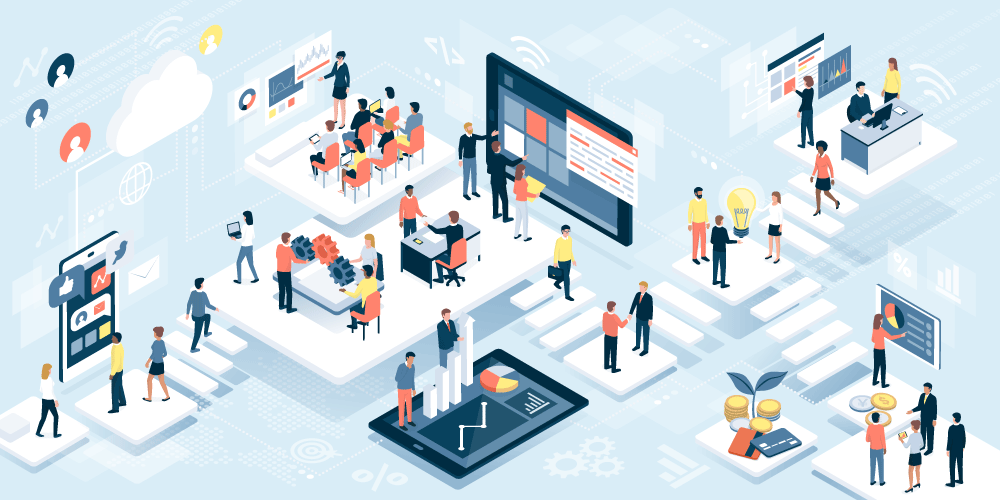
雇用保険の財源不足や2020年5月に成立した年金制度改正法などによって、2022年4月と10月にそれぞれ段階的にさまざまな労務に関する法律が改正されることとなりました。その改正内容は雇用主である企業はもちろんのこと、企業で働く労働者もあらかじめしっかり把握しておく必要があるでしょう。そこで今回は、とりわけ2022年の改正はどの法律のどの部分なのかを具体的に解説します。
雇用保険料率が引き上げられる!
新型コロナウィルスの影響で雇用保険の財源が不足していることから、2022年3月に国会で改正雇用保険法が成立しました。この法改正には2022年4月と2022年10月にそれぞれ段階的に雇用保険料率を引き上げることが含まれています。2022年4月の改正内容は事業主負担分の保険料引き上げ、2022年10月の改正内容は労使折半である失業給付や育児休業給付の保険料率引き上げです。その結果、以下のようになります。
- 2021年度の雇用保険料率労働者負担分は給料の0.3%、事業主負担分は給料の0.6%
- 2022年4月から9月労働者負担分は給料の0.3%、事業主負担分は給料の0.65%
- 2022年10月以降労働者負担分は給料の0.5%、事業主負担分は給料の0.85%
社会保険の適用範囲が拡大する!
2020年5月に成立した年金制度改正法により、社会保険の適用範囲が2022年10月と2024年10月に拡大されることとなりました。変更点は2点あります。ひとつは企業の規模です。2021年度までは短時間労働者を社会保険に加入させなければならない企業は従業員数が501人以上でしたが、2022年10月からは従業員数101人以上、2024年からは従業員数51人以上の企業も含まれます。また、短時間労働者の勤務期間に関しては、2021年度までは契約期間が1年以上の場合に社会保険に加入しなければならないことになっていました。しかし、2022年10月からは契約期間2カ月以上の労働者に社会保険への加入が義務付けられることとなります。
育児休暇に関する制度も変わる!
2021年に改正された育児・介護休業法により、2022年4月以降3段階にわたって育休制度の変更が行われることとなりました。とりわけ2022年10月の改正は育児・介護休業法だけでなく、雇用保険法や社会保険各法などさまざまな法令が関わる改正です。そのため、企業の人事労務担当者は改正内容をしっかり把握しておきましょう。
出生育児休業制度(産後パパ育休)の創設
2022年10月以降、通常の育児休業制度とは別に出生育児休業制度(産後パパ育休)が創設されることとなりました。この制度は出産する女性以外の男性や、あるいは養子を迎える女性が子の出生後8週間以内に最長4週間取得できるというものです。主に男性の育休取得の推進を図ることを目的とした制度であり、通常の育休とはまた別のものになります。そのため、男性、または養子を迎える女性は出生育児休業と育児休業の両方を取得することも可能です。申し出期限は休業の2週間前までとなっています。また、この制度の創設によって育児休業の特例制度であるパパ休暇は廃止されることとなりました。
育休制度の分割取得が可能に
それまで育休制度は分割して取得することができませんでしたが、2022年10月以降は2回に分けて取得することができることになりました。育休制度の場合、申し出はそれぞれの取得の際に行うことができます。この変更により、共働きの世帯などは夫婦で育休を交代でき、家庭の事情に合わせた育休の取得が可能となるでしょう。出生育児休業制度も2回に分割して取得することが可能です。ただし、こちらの場合は、最初にまとめて申し出ることが必要なので注意しましょう。
育児休業給付金の見直し
出生育児休業制度の創設に伴い、出生育児休業制度を取得した男性や出産した女性以外の女性は出生育児休業給付金が取得できます。また、育休制度の分割取得が可能になったことを受け、育児休業給付金も分割で取得することが可能となります。
社会保険料免除要件の見直し
2022年10月までは月の途中に短期間の育児休業を取得した場合、社会保険料が免除されないといった問題がありました。社会保険料を免除されるためには月末時点で育児休業を取得していなければならなかったのです。そのことから、2022年10月以降は現状の月末時点に加え、同月内に14日以上の育児休業をしている場合でも社会保険料が免除されることになりました。
改正項目をしっかり把握しよう!
法や制度が改正されると、自社が対象となるのかどうかということや自社で働く従業員の中に対象者はどれくらいいるのかといったことを改めて確認し、把握しておく必要があります。また、育児休業に関しては新制度の創設や既存制度の廃止、見直しなどによって2022年10月以前と以降とでは大きく異なるので企業側はしっかり確認しておくことが大切です。